

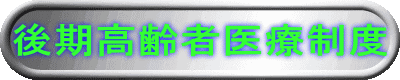
| 後期高齢者医療制度は、平成20年4月に「老人保健法」を「高齢者医療確保法」に改称して発足しました。これにより、今までは各医療保険制度の中に組み込まれていた後期高齢者医療の部分を都道府県単位で切り離して運営していこうという制度になりました。しかし、今後超高齢化社会を迎える中、高齢者医療費は青天井でとても保険料収入や国庫負担だけで手に負えるものではなく、被用者医療制度の保険料に含まれる負担金や国民健康保険の支援分が増額の一途をたどることは想像に難くありません。 |
| ① 制度の概要 1、被保険者 (1)75歳以上の者 (2)65歳以上75歳未満のものであって、一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者 一般的に、被用者医療保険の被保険者であっても被扶養者であっても、75歳に達するとその資格を喪失し、後期高齢者医療制度被保険者資格を取得します。 国民健康保険加入者も75歳に達した日に国民健康保険被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度被保険者資格を取得します。 2、保険者 都道府県単位に設置されている後期高齢者医療広域連合(政令指定都市であっても単独で保険者にはなれず、広域連合に加入しなければならない) 3、保険給付の種類
内容を知りたい場合は表の中の項目から「健康保険の活用」・「国民健康保険の活用」のページの各項目にジャンプできます)。 |
| ② 保険料 1、原則 保険料は別表の通り都道府県単位で定められており、収入に比例して保険料が定められる所得割と、各被保険者それぞれに定額の保険料を賦課される均等割の合計が全体の保険料になっています。 2、例外 (1)低所得者 所得が少ない人は、その所得に応じて、均等割部分の保険料を9割から2割減免されます。 また、所得割部分も所得合計が91万円以下の人について、所得割部分の保険料を5割減免されます。 (2)被用者医療保険被扶養者から切り替わった者 後期高齢者医療制度被保険者資格を取得する前日に被用者医療保険の被扶養者だった者は、それまで全く保険料負担がなかったところへ急に保険料が発生し過度に負担が増加することを防ぐために、均等割部分が9割、所得割部分が全額減免されます(この減免制度は、現在のところ法令に適用の期限の規定はなく、後期高齢者医療制度被保険者取得時に減免対象であれば当分の間は保険料が減免されます)。 3、滞納時の措置 基本的には国民健康保険料の滞納の場合と同じです。 (1)督促等の措置 後期高齢者医療制度の保険料を納期限までに納めないとすぐ取り立てに来る、ということはあまりありません。何か月かして「支払ってないので支払ってください」と督促状が届いて、それでも納めない場合は繰り返し督促し、ある程度期間が経過したら差押通知、最終的に差押と強制執行の手続きが進められます。 (2)滞納した場合の医療給付の取り扱い 1年以上保険料を滞納した場合、役場から保険証の返還を請求され、それと引き換えに「被保険者資格証明書」を交付されます。「被保険者資格証明書」では直接医療機関で医療の給付を受けることはできず、窓口では医療費の全額支払い(10割負担)を求められます。 しかし、「国民健康保険の活用」で挙げた通り、支払った医療費のうち一部負担金(1割又は3割)を除く部分は特別療養費として、役場に申請することにより返還されます。 1年6か月以上保険料を滞納した場合、保険給付を一時差し止められます。この場合、役場はあらかじめ世帯主等に通知して、差し止められた特別療養費等の保険給付の金額から、滞納している保険料の金額を差し引いて強制的に徴収することができます。
|