

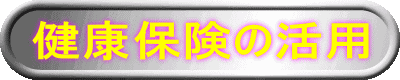
| 毎月給料から保険料を差し引かれて加入している被用者医療保険。皆さんの中には、その給付の内容が、病院で医療費が3割の負担で済むことしか知らない人もいると思います。ここでは、被用者医療保険にどのような給付があり、どのような場合に利用できるか、基本的な知識を身に付けましょう。 |
| ① 被用者医療保険が利用できる場面 健康保険や共済組合の制度が利用できるのは、 (1)私的な傷病で医療を受けることが必要である場合 (2)自己の故意の犯罪行為又は故意に給付事由を生じさせたものではない場合 が基本的な条件です。 (1)に該当しない代表例は労働災害です。労働災害は労働者災害補償保険から給付が行われるため、被用者医療保険からは給付が行われません。 また、健康診断は「傷病で医療を受けることが必要」な場合ではないので、各種医療保険の適用外になります。 (2)に該当する代表例は自殺未遂です。自殺未遂は自らの意思で自らの命を絶とうとする、又は自傷行為を行うものですから、それに対してまで保険給付を行うことはないというのが政府の考え方です(昭.11.1.9保規394号)。 ただし、重いうつ病などの精神疾患が引き起こす自殺念慮による自殺未遂については、基礎疾患があるために生じた傷病であるため、保険給付が行われます。 なお、交通事故は、自損事故の場合は原則として保険給付の対象になりますが、相手方がある事故は「第三者行為による傷病届」を提出しない場合は保険給付の対象にならず、全額自己負担になります(通勤時の事故については労災適用のため元来除外)。交通事故に遭ったときは早めに健保協会に連絡を取って、必要書類を送付してもらって手続をしましょう。 |
| ② 保険給付の種類 保険給付の種類は、大きく現物給付と金銭給付に分けることができ、それらをさらに分けると下表のようになります。 1、療養の給付 病院等(保険医療機関・薬局)で診察を受けたり薬剤の処方を受けたりしたときに支払う一部負担金(1~3割)以外の、9~7割の部分を被保険者・被扶養者に対して医療行為等という現物で給付されるものです。9~7割の部分は加入する被用者医療保険の保険者から病院等に金銭で支払われます。 2、入院時食事療養費 一般の入院患者の場合(※)、1食あたり260円が医療費の他に食事療養標準負担額として加算されます。この食事療養標準負担額以外の部分が入院時食事療養費として食事という現物で給付されます。 ※所得階層により標準負担額が軽減されています。 3、入院時生活療養費 特定長期入院被保険者(65歳以上の療養病床入院患者)が、生活療養に要した費用のうち生活療養標準負担額以外の部分が、入院時生活療養費として生活療養という現物で給付されます。 ※所得階層により標準負担額が軽減されています。 4、保険外併用療養費 保険外診療のうち「評価療養」と「選定診療」と、保険診療が併用された場合に、保険診療部分の一部負担金を除いた「療養の給付」に該当する部分を保険外併用療養費として、医療行為等という現物で給付されます。 5、療養費・家族療養費 次の場合には、療養の給付の代替として療養費を受給することができます。 ア、療養の給付等1~4の給付を受けることが困難であると認める時 →へき地のため保険医療機関がない、資格取得届提出の遅れのため保険証が使えない等 イ、被保険者・被扶養者が保険医療機関等以外の病院等で診療、薬剤の支給等を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認める時 →交通事故等緊急時における保険医療機関以外での診療、海外における急病時の診療(海外療養費)等 〇支給額 原則として、上記の場合に支払った金額の7割(小学校入学前は8割、70~74歳は原則9割) ただし、入院した場合は食事療養費と生活療養費の全額から食事療養標準負担額と生活療養標準負担額を差し引いた額 を支給。 また、上記の場合に支払った金額が、保険者が算定した金額よりも少ないときは、実際に支払った金額から、一部負担金と食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を差し引いた額を支給。 6、訪問看護療養費・家族訪問看護療養費 在宅療養をする患者が主治医を通じて指定訪問看護事業者による訪問看護サービスを受けたときに、サービスの費用のうち患者の一部負担金以外の部分を訪問看護療養費として訪問看護サービスという現物で給付されます。 7、移送費・家族移送費 保険者が次のいずれにも該当すると認めた場合に支給されます。 ア、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと イ、移送の原因である疾病や負傷により移動をすることが著しく困難であったこと ウ、緊急その他やむを得なかったこと ○支給額 最も経済的で、かつ通常の経路及び方法により移送された時の費用の範囲内で、実費を支給。実際に支払った費用のほうが多い場合は、超過分は患者負担となる。 |
8、高額療養費 同一月内の同一医療機関における医療費負担額が一定金額以上になった場合は、一定金額を超える部分について高額療養費として払い戻しを受けることができます。 ア、70歳未満の場合の高額療養費 (1)原則 被保険者・被扶養者が、同一月内に同一の医療機関において支払った医療費の一部負担金等が高額療養費算定基準額を超えたときに、そのを高額療養費として支給します。 上記の「医療費」は一部負担金(患者負担分)の金額ではなく、医療費の全額を指します。 (2)例外 Ⅰ 一部負担金等世帯合算 自己負担額が高額療養費算定基準額以下であっても、同一世帯で同一月内のそれぞれの一部負担金等の額が1件あたり21,000円以上である場合は一部負担金等世帯合算額に算入でき、その合算額が上表の金額を超えれば高額療養費の支給対象に該当します。 Ⅱ 高額療養費多数該当世帯 高額療養費の支給対象に該当した月以前の12か月以内にすでに3回以上高額療養費が支給されている場合は、多数該当として上表右側の金額が高額療養費算定基準額とされ、この金額を超えた分が高額療養費として支給されます。 Ⅲ 特定疾病者の負担軽減 長期間、高額な治療を継続する必要がある疾病(特定疾病)については同一月内の自己負担額が10,000円を超えた場合は、10,000円を超えた金額が支給されます。 ただし、70歳未満の人工透析患者のうち、上位所得者については自己負担額が20,000円を超えた場合になります。 特定疾病は、 の3つが指定されています。 (3)健康保険限度額適用認定証制度 70歳未満の被保険者・被扶養者が入院等により高額の一部負担金を支払わなければならないことが見込まれる場合は、事前に会社を通じて健保協会等に申請し「健康保険限度額適用認定証」の発行を受けて指定した医療機関に提示することにより、同一月内の医療費負担が認定額を限度として不要となり、それ以上は療養の給付同様現物支給になります。 イ、70歳以上の場合の高額療養費 高額療養費算定基準額が下表のように変わります(※多数該当は44,400円)。 (1)個人単位の外来診療 同一月内に負担した一部負担額等の金額が、上表の額を超えた場合はその超えた部分が高額療養費として支給されます。 (2)世帯単位及び入院の場合 同一世帯で同一月内に負担した一部負担金等の額が上表の額を超えた場合はその超えた部分が高額療養費として支給されます。 なお、同一世帯で同一月内に70歳未満の者と70歳以上の者それぞれについて自己負担額がある場合、それらを合算できます。70歳以上の者については全ての自己負担額が、70歳未満の者については1件につき自己負担額21,000円以上のものが対象になります。 9、高額介護合算療養費 世帯内の同一医療保険加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(※1)を合計し、下表の額を超えた場合に、その超えた金額を高額介護合算療養費として支給します。 ア、70歳未満の場合 イ、70歳以上の場合 10、傷病手当金 (1)支給要件 被保険者が私的な傷病が原因で下記の要件すべてに該当する場合は、休業を開始した日から起算して第4日目から原則として休業を終了する日まで、傷病手当金が支給されます。 ※業務や通勤が原因の傷病は労災から休業(補償)給付が支給されるため、健康保険からの支給はありません。 (2)待期期間の考え方 ・原則として労務不能初日から起算する。ただし、所定労働時間終了後はその翌日から起算する。 ・3日間の待期期間は、有給休暇の利用等により会社から報酬の支払いを受けていてもよい。 ・3日間の待期期間は、暦日3日間連続でなければならない。3日間のうち何日かが所定休日に当たっても問題はない。 (3)支給額・支給期間 1日につき、標準報酬日額(別表参照)の3分の2を、支給開始日から最長1年6か月支給されます。 この「1年6か月」は暦の日数でみますから、支給開始日から1年6か月の間に出勤して傷病手当金が支給停止になった期間があっても、支給開始日から1年6か月が経過した日に支給は打ち切りになります。 (4)併給調整 ア、出産手当金 出産手当金を優先支給し、傷病手当金は支給しません(支給額が同じのため差額支給もありません)。 イ、労災保険の休業(補償)給付 前述の通り、休業(補償)給付を優先支給し、傷病手当金は支給しません。ただし、傷病手当金の日額の方が多い場合は、差額を支給します。 ウ、障害厚生年金・障害手当金 障害厚生年金を優先支給し、傷病手当金は支給しません。ただし、傷病手当金の日額の方が多い場合は、差額を支給します。 障害手当金が支給される場合は、本来支給されるはずであった傷病手当金の金額が障害手当金の金額に達するまで傷病手当金を支給停止し、その後傷病手当金の支給残期間があれば傷病手当金を支給します。 エ、老齢・退職年金給付 被保険者資格喪失後、継続して傷病手当金の支給を受けるべき者が、老齢・退職年金給付の支給を受けられる場合はそれらを優先支給し、傷病手当金は支給しません。ただし、傷病手当金の日額の方が多い場合は、差額を支給します。 11、出産育児一時金・家族出産育児一時金 (1)支給要件 被保険者・被扶養者が出産したとき ・出産とは、妊娠4か月(=13週目)以上の出産(生産・早産・死産・流産・人工中絶)を指します。 ・正常分娩・人工中絶は「1、療養の給付」の支給対象外です。 (2)支給額 出生児1人あたり原則42万円(双子の場合は2人分84万円) (3)出産育児一時金直接支払制度・受取代理制度 ともに高額になる出産費用の負担軽減を目的として創設された制度であり、 前者は出産予定の産婦人科に保険証を提示し、その産婦人科から退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意する必要があります。 後者は出産予定日から2か月以内の者が健保協会等に申請することにより、支給額の全額が産婦人科に支払われる制度で、利用できる産婦人科は厚生労働省への届出を行った一部の医療機関に限られます。 12、出産手当金 (1)支給要件 被保険者が、出産の日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から出産の日後56日までの期間、仕事を休業したこと ※出産の日は「産前の期間」に含まれます。 ※労働基準法上、出産前後に労働が絶対的に禁止されているのは産後6週のみ(労働基準法第65条1項・2項)なので、本人の選択によりそれ以外の期間は仕事をして、出産手当金は受給しないということもできます。 (2)支給額 1日につき、標準報酬日額(別表参照)の3分の2 (3)会社から報酬が支払われる場合 原則出産手当金の支給はしません。ただし、報酬の日額が出産手当金の日額よりも少ない場合は差額を支給します。 13、埋葬料(埋葬費)・家族埋葬料 (1)埋葬料・家族埋葬料 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対して埋葬料5万円が支給されます。 被扶養者が死亡したときは、被保険者に対して家族埋葬料5万円が支給されます。 (2)埋葬費 被保険者が死亡したときに、埋葬料を受給すべき者がいない場合は、埋葬を行った者に対し、5万円を限度に埋葬に要した費用に相当する実費が支給されます。
③ 退職後の保険給付 療養の給付など主に現物支給の給付は退職して被保険者・被扶養者資格を喪失してしまえば受給できなくなりますが、下記に示す給付は、一定の要件を満たせば被保険者が退職して資格を喪失しても継続して受給することができます。 (1)傷病手当金・出産手当金 ア、支給要件 ・被保険者資格喪失日前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと ・資格喪失日に傷病手当金又は出産手当金を現に受給している又は支給要件を満たしていること イ、支給期間 原則通りの期間支給 (2)出産育児一時金 ア、支給要件 ・被保険者資格喪失日前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと ・資格喪失日から6か月以内に出産したこと イ、併給調整 被保険者資格喪失後、夫が加入する被用者医療保険の被扶養者になった場合は、自らが加入していた被用者医療保険からの出産育児一時金か、夫が加入する被用者医療保険からの家族出産育児一時金か、どちらかを選択して受給することになります。 (3)埋葬料 次のいずれかの要件を満たす場合は、被保険者であった者により生計を維持されていた者であって埋葬を行う者に、最後の保険者から埋葬料が支給されます。 ア、傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けている者が死亡したとき イ、傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、給付終了後3か月以内に死亡したとき ウ、被保険者であった者が被保険者資格喪失日後3か月以内に死亡したとき |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||