

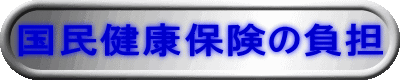
| 「国保は高い」という声をよく聞きます。しかし、実際にはどのように計算されているのか知っている人は少ないのではないでしょうか。ここでは、市町村の国民健康保険料の算出のしくみ及び保険料(税)額と協会けんぽの保険料との比較をしてみるとともに、国民健康保険料を滞納した場合のペナルティについてみていきます。 |
| ① 国民健康保険料の計算式 国民健康保険料(税)の「料率(税率)」・「料額(税額)」は、全国の各市町村で全くと言っていいほど異なりますが、計算方式は大きく分けて2つに分かれ、ほぼ統一されています(各用語は別ページの「注釈」を参照してください)。 1、旧但し書き方式 旧但し書き方式とは、昭和36年から38年までの間、市町村民税の所得割の課税方式として採用されていたものと同じ方式です。当時の地方税法では条文のただし書のところに規定された課税所得金額による算定方法でしたが、現在の地方税法では1項を設けているため、「旧」但し書きと呼ばれます。 計算方法は、 ・給与所得者・年金所得者の場合 →給与所得控除又は公的年金控除後の所得額から基礎控除33万円を差し引いた金額を算定対象額とし、 ・自営業者その他の所得者の場合 →収入総額から各種必要経費を控除した後の所得額から基礎控除33万円を差し引いた金額を算定対象額とし、 を医療分・支援分・介護分のそれぞれについて計算し、それぞれ100円未満を切り捨てて合計したものを国民健康保険料として賦課します。 所得を得ている加入者が同一世帯に2人以上いる場合は、それぞれについて算定対象額を算出し、それを合計して所得割料率を乗じます。介護分については介護保険2号被保険者(40歳~64歳)に該当する加入者がいる場合にその者についてのみ算出します。 社会保険料控除や扶養控除などを全く勘案しない方式であるため、所得割額を多くできるのが市町村側のメリットです。 2、住民税方式(市民税のみ、市民税・県民税合計の2種類あり) この方式は、国の方針で1の旧但し書き方式に統一が進められているため、採用している市町村は全体の2%程度ですが、横浜・名古屋・仙台などの大都市を中心にまだ採用されています。 計算方法は を医療分・支援分・介護分のそれぞれについて計算し、それぞれ100円未満を切り捨てて合計したものを国民健康保険料として賦課します。 住民税課税対象になっている加入者が同一世帯に2人以上いる場合は、それぞれについての住民税額を合計して所得割料率を乗じます。介護分については旧但し書き方式と同様です。 社会保険料控除や扶養控除などを勘案した方式であるため、所得割額を少なくできるのが加入者側のメリットです。 |
| ② 国民健康保険料計算の具体例 実際にモデルケースを挙げて国民健康保険料がいくらになるか試算してみましょう。 「全国都道府県庁所在地国民健康保険料(税)一覧表」のモデルケースで、旧但し書き方式の福井市の場合と、市民税方式の岐阜市の場合を試算してみましょう。 1、福井市 料率・料額は下表のとおりです。
2、岐阜市 料率・料額は下表のとおりです。
モデルケースでの全都道府県庁所在地の試算結果は「全国都道府県庁所在地国民健康保険料(税)一覧表」に掲載していますので、参考までにご覧ください。 ③ 保険料を滞納した場合 協会けんぽの保険料は給料から強制的に天引きされますが、国民健康保険の保険料は自分で支払わなければなりません。そのため、収入が少なかったり、生活費が多く保険料までお金が回らない等、滞納する場合が出てきます。 1、滞納した場合の役場の対応 国民健康保険の保険料を納期限までに納めないとすぐ取り立てに来る、ということはあまりありません。何か月かして役場から「支払ってないので支払ってください」と督促状が届いて、それでも納めない場合は繰り返し督促し、ある程度期間が経過したら差押通知、最終的に差押と強制執行の手続きが進められます。 2、滞納した場合の医療給付の取り扱い 1年以上保険料を滞納した場合、役場から保険証の返還を請求され、それと引き換えに「被保険者資格証明書」を交付されます。「被保険者資格証明書」では直接医療機関で医療の給付を受けることはできず、窓口では医療費の全額支払い(10割負担)を求められます。 しかし、「国民健康保険の活用」で挙げた通り、支払った医療費のうち一部負担金(1~3割)を除く部分は特別療養費として、役場に申請することにより返還されます。 1年6か月以上保険料を滞納した場合、保険給付を一時差し止められます。この場合、役場はあらかじめ世帯主等に通知して、差し止められた特別療養費等の保険給付の金額から、滞納している保険料の金額を差し引いて強制的に徴収することができます。
|