

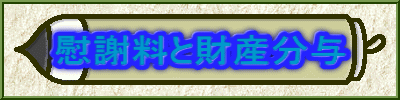
別れ際にはなるべくもめずに済ませたいもの。だって今までさんざんもめたのだから。そんな要望にお応えして、ここで
は慰謝料が請求できる離婚理由と相場、財産分与の範囲について詳しく紹介します。
① 慰謝料
「離婚時の交渉事項」で触れたように、慰謝料は相手に不法行為(民法第709条)があった場合にのみ請求できるのが一般的で
す。しかし、実際には例えば性格の不一致など明確にどちらか一方の責任であると決め難い事由であったとしても、夫婦双方の責
任の度合いで慰謝料請求の可否を決することが多くなっています。
また、協議離婚・調停離婚・離婚訴訟の和解勧告では、早く別れたい方が相手を納得させるための「解決金」名目で一定額を支払
うということも少なくないようです。
1、慰謝料決定の基準…当事者個々の事情によりますが、決定のために考慮される事項としては下記のものがあります。
・財産分与の金額→多ければ慰謝料は少なく
・精神的苦痛の度合い→大きければ慰謝料は多く
・有責性の度合い→自分にも責任があれば慰謝料は少なく
・当時の経済状態→相手の資力が高ければ慰謝料は多く
・その他、婚姻期間、別居期間、離婚に至った経緯、年齢、性別、職業、社会的地位、婚姻生活における夫婦の協力度、子の有
無、親権の帰属、養育費の金額、離婚後の扶養の必要性など
2、慰謝料の相場
1、の基準を多方面から勘案して同じ離婚事由でもその当事者ごとに異なる金額がはじき出されますが、一般的な相場としては
財産分与を含めて、200万円から500万円の範囲内と考えておいた方がいいでしょう。当然、1、に挙げた基準によりここに変化
はしますが、平均的な離婚での交渉ではこの金額に落ち着くことが多いようです。
ちなみに、芸能人が離婚するときの慰謝料が高額なのは、1、に挙げた「職業、社会的地位」並びに「離婚に至った経緯」によるとこ
ろが大きいと推測されます。
3、慰謝料請求のために必要なこと
慰謝料を請求するには、
・慰謝料の請求事由の正当性を示す証拠を集めること
・慰謝料は離婚前に請求すること
の2点が必要です。
1点目は読んで字の如く、相手が言い逃れできないように尻尾をつかんで離さないような証拠を集めなければなりません。
2点目は必ずしも離婚前でなければならないということはありませんが、離婚成立後は相手が交渉を拒否したり金額を値切られたり
するので、できれば離婚前に請求することが望ましいと言えます。
② 財産分与
夫婦の財産は下記の3つに分けることができ、そのうち財産分与の対象となるのは2・3です。
1、特有財産…婚姻前から各自が所有していたもの、及び婚姻後一方が贈与・相続で得たもの。
2、共有財産…夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。
3、実質的共有財産…結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
1、特有財産
お互いの婚前からの預貯金、所有資産は特有財産として財産分与から原則除外されます。例外として、一方の特有財産を維持す
るため他方が相当な寄与をした場合には、特有財産の中からも財産分与が認められる場合があります。
2、共有財産
原則として夫婦の合意の下に築いた財産を指し、共働きの場合に双方生活費を支出した残金を貯金していたものについては特有
財産となるので財産分与の対象にはなりません。その他、
・子のための預貯金→夫婦関係の破綻前のものは共有財産、破綻後は預貯金していた者の特有財産
・ヘソクリ→夫婦共同生活のための預貯金と同等のものなので共有財産
・借金・ローン→個人目的で借りた金銭については特有財産、夫婦共同生活のために借りた金銭については共有財産
となります。
3、実質的共有財産
婚姻中に購入した自動車や住居、有価証券などが対象になります。
自動車や住居のように分割不可能なものの財産分与は、それらを継承する者から他方に現金で清算する形をとります。
4、専業主婦(夫)の財産分与と共働きの財産分与
共働きの場合は夫婦双方働いて共に財産を築いてきたということが明白であるため、財産分与の割合は50%になることがほと
んどですが、専業主婦(夫)の場合は夫(妻)の労働及び財産の増加に対する寄与度を明確にし難いため、争うことが多いところ
でもあります。
家庭裁判所の判断では、多くの場合は財産分与の割合を30~50%の間に設定しているようです。その根拠は、家事労働の財産
形成への寄与度により判断されています。専業主婦(夫)で分与割合50%が認められるのは、不動産等を購入したときに妻(夫)
も現金を出した場合や、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮した場合など、特殊なケースに限られています。
③ 年金分割
平成19年4月以降に離婚した場合、離婚の際に妻が請求することにより、夫の年金受給権の一部を譲受させることができる制度が
設けられています。これを「年金分割」と言い、2つのパターンに分かれます。
1、合意分割
婚姻期間全てを対象に、夫が厚生年金・共済年金の加入者であった期間の厚生年金・共済年金部分の年金受給権の最大50%
を妻に分割するよう請求し、夫との協議・合意により定められた割合の年金受給権を妻に分割するものです。
対象期間が長く夫の合意を得られればそこそこの額の年金受給権が分割されるのがメリットですが、合意分割には夫の合意が不
可欠であるため要求した分割割合が必ずしもそのまま認められる保障はないというのがデメリットです。
2、3号分割
平成20年4月以降離婚までの期間のうち妻が国民年金第3号被保険者であったを対象に、夫が厚生年金・共済年金の加入
者であった期間の厚生年金・共済年金部分の年金受給権の50%を妻に分割するよう請求し、夫の意向に関係なく強制的に夫の
年金受給権の50%を妻に分割するものです。
まだ制度が始まって年数が経過していないため分割される金額としては少額なのがデメリットですが、定められた期間の年金受給
権の50%の分割が確保されるというのがメリットです。