

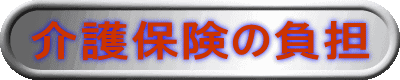
| 介護保険も「保険」制度であるため、国・自治体の交付金と被保険者が支払う保険料で運営されています。給付に関する費用は、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%と公費で合計50%、そして保険料収入で残りの50%が賄われています。第1号被保険者の保険料は3年に1度、第2号被保険者の保険料は毎年見直されるため、今後、受給者が増えれば保険料は確実に上がっていきます。 |
| ① 第2号被保険者の保険料 40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者は医療保険の保険料と共に介護保険料を徴収されます。 協会けんぽ被保険者の場合は各都道府県ごとの健康保険料率に加えて全国一律で1.51%(労使折半)、国民健康保険加入者の場合は「医療分」・「支援分」に加えて「介護分」として各市町村・各組合で定められた料率・料額を賦課されます。 被用者医療保険加入者の場合はほぼ強制的に徴収されますが、国民健康保険加入者は国民健康保険料を滞納すれば介護保険料も同時に滞納になるため、後述するペナルティを受ける可能性があります。 |
| ② 第1号被保険者の保険料 65歳以上の全ての人は第1号被保険者として、それまでの医療保険との合算という形態から、介護保険料のみ単独で計算・徴収が行われるようになります。 1、保険料の計算 介護保険の運営は各市町村で行われているため、各市町村ごとに保険料が異なります(各都道府県庁所在地については別表参照)。 保険料は、まず介護保険運営のためにかかる経費から保険料の基準額を算出し、その基準額に所得階層に応じた倍率を乗じて算出します。生活保護者は基準額の半額程度、所得が最高段階の者は基準額の2倍程度の保険料になります。 ※各都道府県庁所在地以外の市町村の介護保険料は各市町村のホームページでご確認ください。 2、保険料の徴収方法 保険料の徴収方法は、受給している年金の額により2通りに分かれます。 (1)特別徴収 受給している年金の年額が18万円以上(=1回の振り込みが3万円以上)の第1号被保険者は、保険料の年額を6回の年金支給日に合わせて分割して、給与所得者同様年金から天引きして徴収します。 強制的に天引きなので払い忘れや滞納の心配がないというメリットがあります。 (2)普通徴収 受給している年金の年額が18万円未満(=1回の振り込みが3万円未満)の第1号被保険者は、保険料の年額を通常10回(市町村により異なる)に分割して納付書又は口座振替で支払います。 払い忘れや滞納の恐れがあるため、高齢者のみの世帯では納付日の管理が必要不可欠です。世帯主・配偶者は第1号被保険者と共に保険料を連帯して納付する義務を負います。 |
| ③ 保険料滞納のペナルティ 第1号被保険者である要介護被保険者・居宅要支援被保険者については、保険料を滞納すると、特別の事情があると認める場合を除き、下記のペナルティが課せられます。 1、1年以上滞納しているとき 被保険者証の提出を求められ、「支払方法変更の記載」をされます。通常は利用費の1割負担で済みますが、「支払方法の変更の記載」をされている間は、被保険者が一旦全額支払い、別途給付分の還付を役場に請求しなければなりません。 2、1年6か月以上滞納しているとき 1のペナルティに加え、保険給付の全部または一部が差し止められます。 3、2年以上滞納しているとき 役場が保険料徴収をする権利を行使できるのは2年間(介護保険法第200条)の時効にかかると定められており、要介護認定時にこの2年間の時効により保険料徴収権消滅期間がある場合は、給付減額期間を定められて給付割合が9割から7割に引き下げられ、高額介護サービス費等の一部給付を受けることができなくなります。 |