

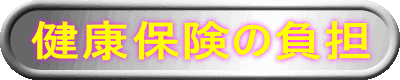
| 健康保険料率は、政管健保の最後は標準報酬月額の8.2%(労使折半、以下同じ)でした。それが平成21年に政管健保が協会けんぽに変わり、平成22年4月には保険料率が一気に1%以上上がり、全国平均9.34%になり、さらに平成23年4月には9.50%まで上がりました。この原因は、医療費が右肩上がりなのに対して、被保険者の賃金が低下し保険料収入が減少しているためです。今後の医療保険政策次第では、保険料率が10%の大台に乗る日もそう遠くはありません。 |
| ① 協会けんぽの保険料率 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに定められています。平成23年度の保険料率は下表のようになっています。 なお、40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険第2号被保険者にも該当するので、この料率に加え、介護保険料率として全国一律1.51%が加算され併せて保険料を徴収されます。 ② 健康保険の保険料 健康保険被保険者は、毎月人それぞれ異なる保険料が給料から天引きされています。 健康保険の保険料は、どのようにして決めるのでしょう? 1、標準報酬月額・標準賞与額 総務・経理の部署では、毎年7月を前にすると、各従業員の4~6月の給料を集計してある書類を作成します。それを7月1日から10日までの間に年金事務所に提出すると、標準報酬月額が決定します。 要は、4月~6月までの給料を合計して平均額(報酬月額)を算出し、表(PDF)に当てはめて標準報酬月額を算出する、という作業を行っているのです。例えば、報酬月額が315,000円の人は、標準報酬月額が320,000円になります。 通常は、この作業により標準報酬月額を決定し、その年の9月の保険料から適用します。 また、賞与が支給された場合は、賞与の支給総額の1,000円未満を切り捨てて標準賞与額とします。 2、保険料の求め方 次の人を例にとって、保険料の求め方を見てみましょう。 <条件>35歳、愛知県在住、健保協会愛知支部管轄の会社に勤務、4~6月の給与総支給額は下表のとおり。 ※たとえ勤務地が東京都であっても、会社の本社が愛知県の場合は愛知県の保険料率が適用されます。 ③ 任意継続被保険者 退職日直前に2か月以上継続して被保険者期間がある人は、会社を退職した後、健康保険被保険者資格喪失日から20日以内に、住所地を管轄する健保協会支部に申請することによって、「任意継続被保険者」の資格を取得できます。 一般被保険者とは異なり、任意継続被保険者は保険料を労使折半できませんから、保険料は全額自己負担することになります。ただし、標準報酬月額は全国の被保険者の平均である28万円が上限として適用されます。 ですから、上記の例の人の場合、任意継続の保険料は 280,000円×9.48%=26,544円/月 になります。 退職後の医療保険の選択肢には、この任意継続被保険者と国民健康保険加入者の2通りがあります。よく、「どちらが得ですか?」と問い合わせをする人がいるようですが、別に述べる「国民健康保険の負担」に示す計算式と併せて比較検討すればすぐに判明する話です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||