

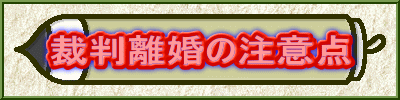
人生の中で裁判を経験する人はそうそういません。しかし、意図せずして離婚に際して裁判を経ることになってしまう
夫婦は年間約2,500組、5,000人に上ります。万が一その中の1組・1人になってしまった場合に心がけたいこと、注意点
について説明しましょう。
① 裁判の提起
裁判を起こすための手続については裁判所HPに詳細が記載されています。
また、訴状の専用様式とその記載例もダウンロードできます。
調停の申立用紙に比べて記載事項が多く複雑なように見えますが、順を追って記入していけば簡単に完成させることができます。
「請求及び申立ての趣旨」(第2面)には、「子との面会交渉権」の欄がないので、面会交渉権についても審理して欲しい場合は「親
権者の指定」の第2項に子との面会交渉権をどのようにしたいか記入しましょう。
「請求の原因等」のうち「3[離婚の原因]」は、調停の申立用紙とは異なり、法定離婚事由が挙げられていますから、たとえ「性格
の不一致」が原因であっても、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に☑を入れて、第3面にその具体的経緯を記入します。
具体的経緯と言っても、「〇月〇日夫婦喧嘩をし、…」と細かく事実を述べるのではなく、「夫には内弁慶なところがあり、会社での
ストレスはみな私や子に当たり散らすことにより発散し…」と、相手方に落ち度がありそれにより夫婦関係を修復すること及び
婚姻関係を継続することが難しくなったという経緯を述べます。
「離婚の原因」の詳細以下は、「請求及び申立ての趣旨」の順番・内容に従って、自己の主張を論理的に述べていきます。主観
的又は推測・曖昧な表現は不適切であり、裁判官に認められません。
最後には必ず「[まとめ]」と題して、「よって,請求及び申立ての趣旨記載の判決を求めます。」と記して締めとします。
訴状で主張するそれぞれの事項に関しては、その主張を正当化するだけの証拠書類を添付することが必要であり、甲第1号証
から順番に番号を振っていきます。
② 訴えられた方(被告人)がすべきこと
裁判が提起されると、被告人には第1回口頭弁論期日指定、訴状・呼出状の送達が行われ、「答弁書」が同封されてそれを返送
するように指示が書面に記載されています。
答弁書についても、裁判所HPから答弁書記載例をダウンロードできます。
被告人は答弁書に、請求の趣旨や請求の原因などに対する答弁を記載する必要があります。また、ここでも訴状と同様に重
要な事実及び証拠を記載し、証拠書類を添付する必要があり、乙第1号証から順番に番号を振っていきます。
もし、この答弁書の送付を怠り、かつ第1回口頭弁論期日に出廷しなかった場合は欠席裁判となり、被告人は原告人の主張を
全面的に認めたものとみなして判決が下されるため、大変不利な事態になってしまいます。
③ 裁判の流れ
裁判所HPにあるように、提訴、答弁書提出を経た後は、
1、口頭弁論
2、争点・証拠整理
3、証拠調べ(当事者尋問など)
を順番に行いますが、親権や面会交渉権が争点になっている場合は、
4、事実の調査
として子からの聞き取り調査を行うことがあります。
これらの手続を経て、口頭弁論終結から約2か月を目安に判決の言渡しが行われます。不服がある者は判決の日から14日
以内に控訴状を判決を受けた家庭裁判所に提出し、地方裁判所への控訴の意思表示をしなければその判決が確定判決となり
ます。
一方、上記手続を経る中で、夫婦双方が自主的に譲歩し、又は裁判官の判断により和解して裁判を終了させることもできます。
④ 裁判離婚の注意点
1、裁判に臨む人の多くは弁護士に代理を依頼しますが、少し法律を勉強すれば必ずしも弁護士の力を借りずとも、本人訴訟で
乗り切ることができます。
弁護士費用の目安は、請求金額300万円以下の場合、着手料として請求金額の8%、成功報酬(勝訴時の報酬)として判決に提
示された金額の16%(東京第二弁護士会HPより)ですから、判決で請求通り300万円の支払いを受ける内容で勝訴が確定した場
合は、全部で72万円の費用を支払う計算になります。
しかし、相手が弁護士を立ててきた場合は無理は禁物です。こちらも弁護士を立てて応戦し、最低でも敗訴は防ぎましょう。
2、裁判は調停以上に証拠に基づいた論理的説明を求められます。逆に言えば、裁判官は証拠に基づかない主張は聞くに値し
ないと判断すると考えておいた方が無難でしょう。
3、裁判では、普段と違う雰囲気に尻込みしてしまったり舞い上がったりして、自分の言いたいことの半分も言えない人がいます。
そうならないように、第1回口頭弁論期日までの間に自分が主張すべき内容をまとめた自分だけの資料を作成し、尻込みしても
舞い上がってもそれを見れば全て確実に主張できる準備をしておきましょう。
4、裁判は、提起から判決言い渡しまで1年程度かかると言われています。
しかし、最近は裁判期間の短縮化が図られ、事前の「準備的口頭弁論」、「弁論準備手続」そして「書面による準備手続」の争点整
理手続が設けられ、その他訴訟の進行に関して必要な事項について協議する「進行協議期日」も設けられています。
その一方で、これらの期日において充実した審理を行うことができるようにするため、準備書面を期日に余裕を持たせて準備す
ることが当事者に求められます。