

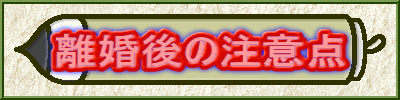
離婚した夫婦はさまざまな経緯を経て、それ以降は他人としてそれぞれの次の人生を歩み始めます。しかし、歩み始め
て終わりではありません。ここからが第二のスタート、そして、離婚のときに交わされた書面の内容が生きてくるのは
これからなのです。
① 離婚後の手続
1、子の氏の変更許可審判(手続詳細)
離婚届を提出するとき、夫婦のうち籍を抜く方は離婚後に名乗る姓を選択しました。しかし、籍を抜く方が親権者になっており婚姻
前の姓に戻った場合は、子の戸籍はまだ他方の戸籍に入ったままなので、家庭裁判所に子を自分の戸籍に移し、自分の婚姻前
の姓を名乗らせることについて許可を得る必要があります。
許可の審判が下った後は、審判書謄本と入籍届を併せて市町村役場に提出すればこの氏の変更手続が完了します。
2、再婚時の養子縁組
離婚時に子を引き取った親権者が再婚する際には、親権者と再婚相手とは親族関係が発生しますが、子と再婚相手とは当然に
は親族関係が発生しません。
そこで、子と再婚相手との親族関係を発生させたいときは、市町村役場に養子縁組届を提出すれば手続は終わりです。(再婚相
手から見て)配偶者の子は、家庭裁判所の許可を得なくても養子にできます(民法第798条但書)。
養子は実子と同じ権利をもちます(民法第809条)。よって、養子縁組をした子は親が3人できたことになり、実親・養親ともにその
相続人になることができます。
3、社会保険関係
離婚後は、当然元配偶者とは別世帯を形成して生計を営みますから、独自に健康保険・年金制度に加入する必要があります。
離婚前から継続して被用者保険制度・年金制度に加入している人は氏名・住所・扶養家族の変更届を勤め先に提出し、離婚時に
無職である人は、新たに国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。これらへの加入手続は各市町村役場で行います。
詳細は「国民健康保険の加入」及び「年金加入の義務」で説明します。
② 相手が離婚協議書・調停調書・判決書で決めた養育費を支払わない
相手が養育費を支払わない…、そんなことはザラです。そんな人でなかったら離婚なんかしません。離婚時の決定事項は反故にさ
れて当然、それぐらいの覚悟でなければなりません。しかし、暮らしていくにはそんなことを言ってはいられません。約束を反故にさ
れた場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
1、公正証書で離婚協議書を作成した場合
「協議離婚の注意点③離婚協議書を作成する」で説明した通り、公正証書で離婚協議書を作成した場合は裁判所の許可なく、公
正証書謄本を公証人の手によって相手方に送達することにより送達証明書を発行してもらい、公正証書の末尾に執行文を付与し
てもらいます(債務名義にする)。これを裁判所に持参して第三債務者(給与支払者や預金口座のある金融機関など)を指定して差
押の申立をすると、裁判所から債務者と指定先に差押命令が出され、指定先から離婚協議書に定めた債権に相当する金額が送
金されてきます(手続詳細:裁判所HP((2)イ債権執行手続参照))。
2、調停調書・判決書の場合
調停調書・判決書も公正証書で作成し執行文を付与された離婚協議書と同様に債務名義ですから、1、に示すように裁判所に差
押の申立をすることになります。
3、一般の離婚協議書の場合
一般の離婚協議書の場合は、法的拘束力が何もないため、債務名義を一から取得する必要があります。
ア、債権者が裁判所に支払督促申立書提出
イ、裁判所が支払督促発布
ウ、2週間待つ
エ、債権者が裁判所に仮執行宣言申立書提出
オ、裁判所が仮執行宣言付支払督促発布
カ、2週間待つ
キ、債権者が債務名義を取得
ク、1に示す通り、裁判所に差押の申立をする
といった手順で差押に向けて着々と手続を進めていかなければならないのですが、ウ・カで相手が異議申立をすると、裁判に移
行します。
③ 子との面会を拒否される
離婚協議書などで定められた子との面会交渉権は、親権者は子の福祉・利益上の理由等、特段の事情がない限り拒むことはでき
ません。にもかかわらず、不当に面会を拒まれる場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」の申立をします。
申立後は、離婚調停と同じく調停の期日を指定され、調停室で話し合いを行います。話し合いがまとまらない場合は、裁判官で
ある家事審判官が、子に関わる一切の事情を勘案して審判を下すことになります。
④ その他のトラブル
①~③に挙げたトラブルの他、離婚後に起こりうるトラブルとしては、
1、子を監護していない親が子を連れ去ったとき
→家庭裁判所に「子の引き渡し調停」の申立をする
2、親権をもつ親が親権者として不適切であると認められるとき
→家庭裁判所に「親権者変更調停」の申立をする
3、離婚時に年金分割の請求を忘れていたとき
→離婚成立日から2年以内に家庭裁判所に「年金分割の割合を定める審判」の申立をする
4、その他離婚後における元夫婦間の様々なトラブルがあったとき
→家庭裁判所に「離婚後の紛争調整調停」の申立をする
といったことがあります。各リンク先の手続詳細に従って手続をしましょう。