

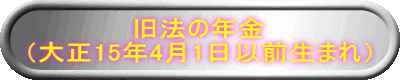
| ここまでお話ししてきたのは、ほとんどが昭和61年4月2日以降に60歳を迎えた、大正15年4月2日以降生まれの人が対象の新法の内容でした。それに対して、ここでは旧法対象者つまり大正15年4月1日以前生まれの人及び昭和61年4月1日以前から旧法の年金を受給していた人の老齢年金・通算老齢年金を少々見ておきましょう。 |
| ① 旧国民年金と新国民年金 1、名称の対比 2、老齢年金と通算老齢年金 ア、要件の差 両者の要件の差は加入年数です。大正14年4月2日~大正15年4月1日生まれの人は、加入期間が20年以上であれば老齢年金、20年未満であれば通算老齢年金です。ただし、生年月日が1年さかのぼるごとに加入年数要件が短縮され、生年月日によって10年~20年の間で老齢年金か通算老齢年金かの差が生まれます。また、通算老齢年金は1つの年金制度に1年以上加入していなければなりません。 イ、支給額の差 老齢年金も通算老齢年金も、基本支給額は同じ計算式で算出します。 これが基本の式です。大正9年度生まれの人が最大限の19年間保険料を納付した場合は、 2,576円×228か月×0.981=576,169円 になります。 しかし、老齢年金にはこれに加えて特別加算が付きます。 この人は15年間加入すれば老齢年金になるので、特例加算として、 997円×(300か月-228か月)×228か月÷228か月×0.981=70,420円 が付きます。よって、合計646,600円の老齢年金が受給できます。
|
| ② 旧厚生年金と新厚生年金 1、名称の対比 2、老齢年金と通算老齢年金 ア、要件の差 厚生年金も加入年数で2つに分けられています。 (1)老齢年金 ・加入年数が20年以上の者 ・男子40歳、女子35歳以降の加入年数が15年以上の者 (2)通算老齢年金 ・1つの年金制度に1年以上加入していること ・他の年金制度と合わせて一定期間以上の加入歴があること イ、支給額の差 老齢年金は3階建て、通算老齢年金は2階建てで構成されています。 (1)老齢年金 (2)通算老齢年金 定額部分・報酬比例部分の2階建てになっており、加給年金はありません。また、定額部分の240か月の最低月数保障はありません。 |
| ③ 通算老齢年金のまとめ 1、受給要件 2、通算老齢年金と老齢年金との違い
|