

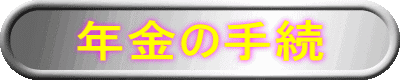
| 「私も60歳になったからいよいよ年金がもらえるわ!」そう言って年金が振り込まれるのを楽しみにしていたA子さん。しかし、待てど暮らせど年金の「ね」の字も振り込まれる気配はありません。そう、A子さんは「年金をください!」と年金機構に請求していなかったのです。 各種年金を受給するためには、原則として「裁定請求」が必要です。以下「裁定請求」について見ていきます。 |
| ① 書類の準備 年金の裁定請求には、意外と多くの書類が必要です。一つ一つ漏れの内容に準備し、一発で裁定請求をクリアできるようにしましょう。 1、老齢年金の裁定請求の場合 配偶者や18歳年度末終了前の子がある場合は、その身分関係や生年月日、生計維持関係の証明書類が必要になります((4)・(5)・(9))。また、子が20歳未満の障害者である場合には診断書等((6))、他の公的年金制度から年金等を受給している場合はその証書の写し((7))、が必要です。 なお、国民年金の任意加入期間に任意加入していなかった場合は、それぞれ次の書類が必要です。 ア、配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人 →配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類 イ、配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人 →配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し ウ、本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人 →本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し エ、その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類 2、障害年金の裁定請求の場合 配偶者や18歳年度末終了前の子及び子の障害の関係や、他の公的年金の受給権関係の書類は老齢年金と同様です。また、国民年金の任意加入期間未加入の書類についても同様です。 3、遺族年金の裁定請求の場合 遺族年金は、死亡者と請求者の2人分の書類を準備しなければならないため、書類の数が他の2つに比べて多くなっています。 しかし、その他は他の2つと同様です。
|
| ② 各年金の裁定請求先 各年金の裁定請求書類がそろったら、いよいよ裁定請求をします。 裁定請求先は、その年金の支給事由が発生した当時加入していた又は最後に加入していた年金制度により異なります。 1、国民年金だったとき (1)老齢年金 ・被保険者期間には国民年金第1号被保険者期間しかない→住所地の市区町村役場の国民年金担当部署 ・被保険者期間には第3号及び厚生年金保険被保険者期間等が含まれる→住所地を管轄する年金事務所 (2)障害年金 ・裁定請求日において最後に加入していた年金が国民年金であった→住所地の市区町村役場の国民年金担当部署 (3)遺族年金 ・国民年金第1号被保険者が死亡した場合→住所地の市区町村役場の国民年金担当部署 ・老齢年金受給権者が死亡した場合→住所地を管轄する年金事務所 2、厚生年金だったとき (1)老齢年金 →会社の所在地を管轄する年金事務所 (2)障害年金 ・裁定請求日において最後に加入していた年金が厚生年金であった→会社の所在地を管轄する年金事務所 (3)遺族年金 ・厚生年金保険被保険者が死亡した場合→会社の所在地を管轄する年金事務所 ・老齢年金受給権者が死亡した場合→住所地を管轄する年金事務所
|
| ③ 不服申立(審査請求・再審査請求) 共済を除く老齢年金や遺族年金の裁定は、それぞれ支給開始年齢に達したことや被保険者等が死亡したことといった、明確かつ普遍的事由によるため、不服申立を行う人はほとんどいません。 一方、問題が起こりやすいのは障害年金です。障害年金の裁定は診断書の書き方一つで大きく変わってしまいますので、医師とよく相談の上作成してもらう必要があります。裁定結果に納得がいかない場合は、不服申立を行うことができます。 1、審査請求 裁定結果が出たことを知った日から60日以内に、各地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。 請求窓口は、各地方厚生局、日本年金機構各地方ブロック本部又は各年金事務所です。 審査請求には所定の様式があるため、審査請求を希望する場合は、まず社会保険審査官に電話して「審査請求をしたい」と伝えましょう。数日後に審査請求書が郵送されてきますから、それに必要事項を記入することになっています。 2、再審査請求 審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から60日以内又は審査請求をした日から60日以内に決定がないときに、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。 請求窓口は、厚生労働省社会保険審査会です。 再審査請求は裁決が出るまで平均1~2年かかる上、意見陳述のために東京まで出向かなければならず、地方在住者や障害者には大変な負担となるのが欠点です。 再審査請求で不服申立の内容が容認される率は、平成22年度に裁決があったうちのです。ここ10年間ずっと再審査請求の件数は増加し続けていますが、容認される件数自体はさほど変化がないため、相対的に容認される率が下がっています。 なお、3か月以内に裁決が出ない場合には、訴訟の提起をすることができます。 |