

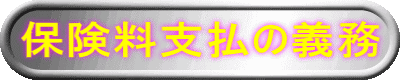
| 国民年金は全国民共通の年金であることは先に見た通りです。厚生年金被保険者・共済保険加入者は有無を言わさず給料から天引きされていき、第3号被保険者は個人負担なしで保険料納付済扱いになります。 問題は第1号被保険者です。保険料の支払は被保険者の義務であることを改めて確認し、保険料を支払わないとどのような不利益があるか見ていきましょう。 |
| ① 国民年金保険料納付率の現状 国民年金保険料は、第1号被保険者であれば本人が毎月必ず納めなければならない(国民年金法第88条1項)と定められている他、世帯主及び夫婦の一方は本人と連帯して保険料納付の義務を負っています(同条2・3項)。 しかし、平成22年度の第1号被保険者1947万人のうちの納付率は、前年度比△0.7%の59.3%、同時期の保険料全額免除者数は551万人となり、保険料納付の義務を果たした又は果たしたとみなされる第1号被保険者は、合計1617万人になります。 あれ?あとの330万人は…?。そう、足りない330万人が未納(2年以上、321万人)又は未加入(9万人)になっています。未納のまま放っておくと、どうなってしまうのでしょう…。 |
② 未納により被る不利益 国民年金保険料を未納のままにしておくと、次のような不利益を被ることになります。 1、未納期間は保険料納付済期間に算入されない 後で述べるように、老齢年金を受給するためには最低25年=300か月の保険料納付済期間が必要です。未納期間はこの期間に算入されないので、未納のまま放置し続けると最低ラインの300か月を満たすことができず、老後に無収入になるという事態に陥る可能性があります。 2、障害者になったときの生活保障が全くない 「年金の仕組み」で説明した障害年金には、受給のための要件の一つに「保険料納付要件」があり、一定の条件を満たさない場合は、一定以上の障害を心身に負っても年金制度からは何らの生活保障も行われないことになっています。 3、死亡したときの遺族保障が全くない 妻と幼い子どもを遺して死んでしまったときには遺族年金の制度がありますが、遺族年金にも受給のための要件の一つに「保険料納付要件」があり、障害年金同様一定の条件を満たさない場合は、遺族に何ら生活保障を残すことができずに終わってしまうことになります。 4、悪質な未納者には容赦なく財産差押処分 2010年8月、当時の厚生労働大臣により、 ・所得が1,000万円以上 ・2年以上国民年金保険料を滞納している ・財産を隠している可能性がある の3つの条件を満たす第1号被保険者を対象に、国税庁に財産の差押えを委任しました。 この条件を満たすのは400人程度とみられていましたが、今後も悪質な未納者には差押処分を強化していく姿勢を日本年金機構も示しています。 なお、国民年金保険料の差押え処分は国民年金法第95条により国税徴収法の例により行うことが認められています。 |
③ 払いたいけれど払えない場合は? 「支払わなければならないのは重々承知しているが、生活が苦しくてとても保険料に回せるお金がない!」 そんな人は、市町村役場で必ず保険料の免除申請をしましょう。 の各制度が利用できます。ただし、それぞれの制度につき、所得制限(年金機構HPへリンク)があります。 1・2は10年の間に追納しなければ将来の年金額を増やすことができません。 3の免除期間は正規の年金額の2分の1(国庫負担分)が保障され、免除の割合に応じてさらに年金額が増えることになります。10年の間に追納すれば正規の年金額まで増やすこともできます。 いずれの制度も免除等を受けている期間は未納とはならず、各年金支給の保険料納付要件に「合算対象期間」として加算されます。 |
④ 事業所の厚生年金適用逃れ・不当な加入拒否 会社等が下記の要件のいずれかを満たす場合は、必ず厚生年金に加入しなければなりません(強制適用事業所)。この要件のいずれにも該当しない会社等は任意適用事業所です。
要件の「従業員」は被保険者となるべき従業員だけではなく、被保険者にならない従業員も含まれます。 ア、通常、強制適用事業所で働く70歳未満の正規職員は厚生年金の被保険者になります。被保険者資格取得日は入社日です。近年、「試用期間中は社会保険には入れない」という会社が目立ちますが、 〇入社から2か月以内の試用期間を定めて雇用契約し試用期間終了後改めて本採用の契約を結ぶ場合はそれが認められますが、 〇入社時の雇用契約の内容で雇用の期間の定めがない又は契約期間が2か月超である場合はそれは認められません。 イ、短時間労働者(パート・アルバイト等)については、下記の要件をいずれも満たす場合は、適用事業所の事業主はその労働者を厚生年金に加入させなければなりません。 やはり、近年経費削減のため、この要件を満たす短時間労働者又はフルタイムパート・アルバイトでさえ厚生年金に加入させない事業所が増えています。短時間労働者の皆さんは、自分が上記の要件をいずれも満たしているか確認し、満たしているにもかかわらず厚生年金に加入させてもらえない場合は労働者の権利として会社に加入を申し入れましょう。 |