

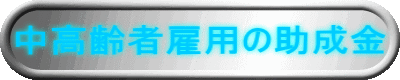
| 年金の支給開始年齢が引き上げが始まった当時、定年退職は60歳が当たり前だったため、何とかして定年年齢を65歳まで引き上げるか、雇用形態は変わっても何らかの形で働き続けて収入が途切れることがないように企業に求めました。そのための助成が「定年引上げ等奨励金」であり、高齢失業者の雇用に対する「特定求職者雇用開発助成金」です。 現在では定年の目標が定年制度自体の撤廃または65歳以上もしくは70歳以上になっています。ここでは、下記の助成金を取り上げます。
|
| 当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。 |
| ① 特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金) 中高年齢者を始め、障害者や母子家庭の母等就職困難な求職者を雇い入れた事業主に支給されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 高年齢者雇用開発特別奨励金(特定求職者雇用開発助成金) 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用することが確実で1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れた事業主に支給されます。
|
|||||||||||||||||||||
| 半年ごとの支給申請はどうしても忘れがち。しかし、各種助成金申請代行をはじめ、業務のご相談だけでも随時承ります。ご希望の方は、下記リンク「相談したい」からお問い合わせください。 |
| ③ 中小企業定年引上げ等奨励金(定年引上げ等奨励金) 65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員70歳以上までの継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止をした事業主に支給されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ 高年齢職域拡大等助成金(定年引上げ等奨励金) 希望者全員が65歳~70歳以上まで働くことができる制度の導入に合わせて、高年齢者の職域拡大や雇用管理制度構築等の取り組みを実施した事業主に支給されます。
|
| 計画書の内容や作成の方法、そろえる添付書類がよくわからない…。しかし、各種助成金申請代行をはじめ、業務のご相談だけでも随時承ります。ご希望の方は、下記リンク「相談したい」からお問い合わせください。 |
| ⑤ 建設業離職者雇用開発助成金 建設業界以外の事業主が、建設業に従事していた45歳以上60歳未満の離職者を新たに雇い入れた事業主に支給されます。
|
| 半年ごとの支給申請はどうしても忘れがち。しかし、各種助成金申請代行をはじめ、業務のご相談だけでも随時承ります。ご希望の方は、下記リンク「相談したい」からお問い合わせください。 |
| ⑥ 職場適応訓練費 実際の職場で作業について訓練を行うことにより、訓練終了後、その事業所に常用雇用されることが期待されるときに、職場適応訓練を受託した事業主に支給されます。
|
|||||||||||||||||