

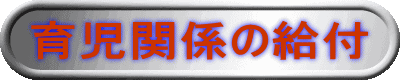
| 産後休業が終わると働きに出る人は従来通り賃金を得ることになりますが、引き続き育児休業に入る人は原則勤務先から賃金を得られないままです。そこで、雇用保険からは給付金を、健康保険・厚生年金からは保険料の免除を行うことにより、育児休業取得者には経済的援助を行っています。 |
| ① 育児休業基本給付金(雇用保険法第61条の4) 平成22年3月末までに育児休業を開始した人については、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金に分けて支給されていましたが、同年4月以降に育児休業を開始した人についてはこの2つを一本化し、新「育児休業基本給付金」として支給することになっています。 1、支給要件(第1項) 2、みなし被保険者期間(第2項) 育児休業開始日を被保険者資格喪失日とみなして、育児休業開始日前日からさかのぼって1か月ごとに区切られた期間に、賃金支払基礎日数(労働日・有休取得日等賃金が支払われた日数)が11日以上ある期間を、みなし被保険者期間1か月として計算します。 3、支給単位期間(第3項) 育児休業基本給付金は「支給単位期間」について支給されます。 支給単位期間は、通常は育児休業開始日(又は応当日)から翌月の応当日(例:8月15日の翌月の応当日は9月15日)の前日までの期間を指し、育児休業終了日を含む月については応当日(又は休業開始日)から終了日までになります。 4、支給日数・支給額(第4・5項) (1)支給日数 ※計算上、支給単位期間内の実際の日数に関わらず、支給単位期間1か月=30日と換算します。 (2)支給額 ※支給率の本則は40%ですが、特別措置として当分の間50%とされています。 (3)休業開始時賃金日額(第4項) 育児休業開始日前日を離職日とみなして失業時と同様に賃金日額を算出したものを指します。 この場合は、対象者の年齢に関わらず30~44歳の離職者の賃金日額上限額14,340円が適用されます。また、賃金日額下限額は2,330円が適用されます。 したがって、育児休業基本給付金の支給日額は、支給調整がなければ1日1,165円~7,170円、30日で34,950円~215,100円の範囲内になります。 (4)使用者から賃金が支払われた場合の支給調整(第5項) 育児休業期間中に使用者から賃金が支払われた場合は、その賃金額により育児休業基本給付金の金額を調整します。 の値により調整額が決定します。 (5)支給申請(雇用保険法施行規則第101条の13第1項~3項) ア、初回申請…使用者が行うので自分で行うことは何もありません。 ・育児休業給付受給資格確認票 ・(初回)育児休業給付金支給申請書 ・休業開始時賃金証明票 を添付書類(賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写し)と共に事業所を管轄するハローワークに提出します。 イ、2回目以降の申請…使用者が代行する場合と自分で行う場合がありますが、ハローワークでは使用者が代行することを推奨しています。 ハローワークから交付される育児休業給付金支給申請書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。 提出期限は、原則2か月に1回、「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」で指定する支給申請期間の支給申請日までです。 (6)パパママ育休プラス制度の特例 同一の子につき夫も育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間、育児休業基本給付金を受給することができます。 また、妻の産後休業中に夫が育児休業を取得した場合は、その期間とは別にもう1度育児休業を取得することができます。 |
| ② 育児休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除等 健康保険料は健康保険法第159条により、厚生年金保険料は厚生年金保険法第81条の2により、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、労働者負担分・使用者負担分ともにその支払いを免除されます。 ただし、厚生年金については保険料を免除された期間も育児休業開始前の標準報酬月額に基づく保険料を支払ったものとみなされ、将来の年金額に加入期間・標準報酬月額ともに反映されます。 |
| ③ 標準報酬月額の育児休業終了時改定 育児休業が終了した時は、育児休業を終了した日において育児休業対象の3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の使用者を経由して保険者等に申出をしたときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で割って算出した金額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します(健康保険法第43条の2、厚生年金保険法第23条の2)。 このとき、厚生年金の扱いにおいて、使用者を通じて厚生労働大臣に申し出た者については、その子を養育することとなった日の属する月から、子が3歳に達した等の事由が発生するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月(その月において被保険者でない場合にあつては、その月前一年以内における被保険者であった月のうち直近の月)の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額をその下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなします(厚生年金保険法第26条)。 |
| ④ その他の助成 ①~③までの措置の他、一定年齢未満の子に対する医療費の助成、乳幼児に対する予防接種の助成、市町村単位での子育て支援や幼稚園の月謝助成など、都道府県ごと・市町村ごとに子どもに対する助成の内容は異なりますので、詳しくはお住まいの自治体のホームページや広報誌、役場窓口でお訪ねください。 |