

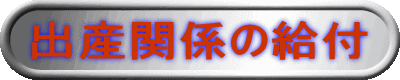
| 妊娠・出産には何かとお金がかかるものです。特に最近は分娩費が高騰し、出産費用の総額が60万円を超えたという話を聞いたことがあります。このように、妊娠・出産に伴う大きな金銭的な負担を軽減するため、国・自治体で出産に関する給付を行っています。 |
| ① 妊婦健診公費補助 産婦人科で妊娠が判明すると、各市町村の保健関係の部署(保健センターなど)で母子手帳の交付を受けます。それとともに、妊婦健診の無料券などの公費補助を受けるための「切符」が交付されます。 これは、妊婦健診が医療保険制度の適用外であるため受診料が高額になり、それを理由に受診を敬遠する妊婦が増えることを防ぐ目的で国が行っている事業で、標準14回分の健診無料券を交付できるだけの予算を各市町村に配分しています。 しかし、市町村ごとの実態は異なっており妊婦健診のための予算を他に流用する市町村があるため、2010年6月発表の厚生労働省の調査で、都道府県ごとの公費助成の額に2.2倍の格差が生じており、最高額は山口県の11.2万円、最低額は大阪府の4.6万円となり、大阪府内43市町村中12市町村で国内最低額の3.5万円を記録しています。 |
| ② 出産手当金 いよいよ出産が近づいてくると、働く妊婦(被用者医療保険の被保険者に限る)は産前産後休業に入ります。労働基準法第65条により、産前産後休業は産前6週(多胎妊娠は14週)、産後8週と定められており、特に産後の6週は絶対的就労禁止期間とされています。 この間、ほとんどの企業は賃金の支払いがないため自身の収入が途絶えます。その分を保障するために出産手当金が被用者医療保険制度(協会けんぽ、健保組合、共済組合等)から支給されます。国民健康保険制度は出産手当金の制度自体ありませんから給付はありません。 また、出産に伴い退職した場合は、退職前に1年以上継続して被保険者であって、退職日に出産手当金を受給していた又は受給資格を満たしていたときは退職後も引き続き出産手当金を受給することができます。 1、支給期間 出産予定日から起算して42日前から実際の出産日の翌日から起算して56日後まで、予定日の通り出産すれば14週・98日間です。しかし、出産予定日はあくまで予定であるため前後しますから、実際の出産日までを産前期間、出産日翌日以降を産後期間として、実際の出産日が予定日より遅れた場合はその日数を加算して支給します。 2、支給額 1日当たり、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。土日も関係なく支給されます。 標準報酬日額6,670円(=標準報酬月額20万円)の人の場合、1日の支給額は4,447円、98日間で435,806円の支給があります。 ただし、絶対的就労禁止期間を除く期間に産前産後休業を取得せず通常通り就労した場合や、休業しても上記の支給額を超える賃金の支払いを受けていた場合には出産手当金は支給されません。 3、申請(協会けんぽの場合) 協会けんぽの場合は、 (1)申請書に記入例に従って必要事項を記入し、 (2)産婦人科で医師の意見を記入してもらい、 (3)勤務先に送付して勤務先に休業期間や賃金の額について証明してもらって健保協会へ提出してもらう という手順を踏みます。 なお、申請は98日分を1回で行うこともできますし、一定期間ごとに数回に分けて行うこともできます。ただし、申請できるのは休業したそれぞれの日から2年間です。早めに申請しましょう。 健保組合・共済組合も制度の概要は同じですが、申請書や申請方法が異なる場合があります。加入する健保組合や共済組合に確認して申請してください。 ③ 出産育児一時金(家族出産育児一時金) 前述の通り、分娩には多額の費用を要するため、国民健康保険を含めた各種医療保険制度から被保険者本人及びその被扶養者の出産の事実に対して、出産費用の補助として被保険者本人には出産育児一時金、被扶養者には家族出産育児一時金が支給されます。 1、支給額 協会けんぽの場合、42万円(一部医療機関は39万円)です。 2、支給要件 (1)現に医療保険の被保険者又は被扶養者であり、妊娠4か月(=13週目)以上の出産であること。 (2)退職日以前1年以上継続して被用者医療保険の被保険者であった者が被保険者資格喪失後6か月以内に出産したこと。 ※出産は、生産・死産・流産・人工中絶を問いません。 ※(2)の場合で、配偶者が被用者医療保険被保険者の場合は被扶養者として家族出産育児一時金を受給するか、自分の被用者医療保険の退職後給付を受給するかの選択になります。また、退職後、本人が国民健康保険加入者になった場合は、国民健康保険からは出産育児一時金は支給されず、自分の被用者医療保険の退職後給付の受給を申請するしか選択肢はありません。 3、申請(協会けんぽの場合) (1)申請書に記入例に従って必要事項を記入し、 (2)産婦人科の医師・助産師又は市区町村長の証明を受け(死産・人工中絶は医師・助産師のみ可)、 (3)被保険者の場合は健保協会に郵送する、被扶養者の場合は被保険者の勤務先に提出する という手順を踏みます。出産育児一時金は勤務先の証明欄はありませんから、被保険者の場合、医師・助産師・市区町村長の証明を受けたらそのまま健保協会に郵送して提出します。 4、出産育児一時金の直接支払制度 以前は出産育児一時金は出産後の申請により被保険者に対して支払われる方式のみでしたが、被保険者・被扶養者の一時的な金銭的な負担を軽減するために、保険者から医療機関に出産育児一時金を直接支払う制度が作られました。 支給額・支給要件は従来の方式と同じです。 ただし、直接支払制度にも2種類あり、「直接支払制度」と「受取代理制度」というものです。 「直接支払制度」とは、事前に出産を予定されている医療機関等へ被保険者証を提示し、当該医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意することで、出産費用の請求が保険者に対してなされるものです。 出産費用の金額が支給額を超えた場合は超えた分を被保険者・被扶養者が支払い、支給額を下回った場合はその差額を申請書の提出により保険者から受給することができます(協会けんぽ用申請書及び記入例はコチラ)。 様式は同じですが、保険者が医療機関へ出産費用を直接支払するタイミングによって、直接支払の前に差額の受給を希望する場合は「内払金支払依頼書」として、直接支払の後に差額の受給を希望する場合は「差額申請書」として提出します。 「受取代理制度」とは、出産育児一時金全額を一旦医療機関が代理で受取り、不足分は被保険者・被扶養者に請求し、余剰分は被保険者・被扶養者に払い渡すものです。 この制度を利用できるのは、出産予定日前2か月以内の者で、「出産育児一時金等支給申請書」に必要事項の記入と医療機関の受任同意を受けて保険者に提出した者に限られます。 |