

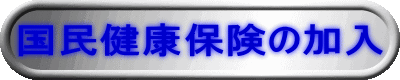
| 国民健康保険は、被用者医療保険の被保険者・被扶養者以外の、自営業者やその家族、無職者、定年後の75歳未満の高齢者等が加入する、市町村又は特定の職域団体が運営する医療保険制度です。国民皆保険の制度が布かれている現在、被用者医療保険の被保険者・被扶養者以外の75歳未満の人は、みんな国民健康保険に加入している、というのが建前です。 |
| ① 加入の手続き 国民健康保険は、次の加入要件に該当した場合には、その日から14日以内に市区町村役場で加入の手続きをしなければなりません。 一番注意しなければならないのが、2の「職場の被用者医療保険の被保険者資格等を喪失したとき」です。 国民健康保険は被用者医療保険とは異なり、自分で役場に出向いて加入・脱退の手続きをしなければならない上、後述するように保険料が割高なため、どうしても加入の手続きを先延ばしにしがちです。 しかし、14日以内に手続きをしないと、手続きをした日以前にさかのぼって医療等の給付を受けられないだけではなく、上記の加入要件に該当した日までさかのぼって国民健康保険料(税)を請求されるという、大きなデメリットがあります。
|
| ② 国民健康保険組合 ①は市町村が運営する地域国保の加入説明でしたが、国民健康保険にはもう一つ、職域組合による国民健康保険組合というものが存在します。例えば、 等の国保組合があります。これらの組合では、その業種に従事する従業員及びその家族を組合員とし、地域国保と全く同じ給付を行いますが、一般的に保険料が定額で地域国保よりも割安な設定になっていることが多いようです。 なお、職域国保の組合員は、地域国保に加入することはできません。 |
| ③ 国民健康保険の加入単位 被用者医療保険は、労働者である被保険者とその家族である被扶養者という形で加入単位が形成されていましたが、国民健康保険ではそのような「扶養家族」という概念はなく、高齢者から生まれたばかりの子どもまで全てが「加入者」として保険料の算出の基礎とされます。 ただし、その世帯における「加入者」の代表は住民票上の世帯主であり、世帯の加入者の保険料を支払う義務を負っています。なお、世帯主が被用者医療保険の被保険者であって、その家族の中に国民健康保険の加入者がいる場合でも、世帯主がその加入者の保険料の支払い義務を負います。 |