

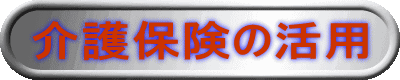
| 介護保険は、病気になって身の回りのことができなくなったので保険給付を受けたい、と言ってすぐ受給できるものではありません。被保険者が申請して市町村が審査をして認定を受けてようやく保険給付を受けることができるようになります。ここでは、その流れと内容を簡単に見ていきます。 |
| ① 介護保険給付の受給要件 介護保険の保険給付を受けようとする場合は、被保険者であって、要介護状態または要支援状態であると認定されなければなりません。また、その認定を受けるためには、市区町村役場に認定の申請をしなければなりません。 1、要介護状態(介護保険法第7条1項) 身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するもの 2、要支援状態(同条2項) 身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について6か月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要支援状態区分のいずれかに該当するもの 3、認定申請と判定 被保険者から認定の申請があると、市町村(通常は指定事務受託法人)は申請者宅に訪問調査に訪れ、また併せて申請者から主治医の意見を提出させて介護認定審査会において要介護・要支援の審査判定を行います。 判定結果は、次の3つに分かれます。 第1号被保険者は身体上又は精神上の障害の原因を問いませんが、第2号被保険者はその原因が特定疾病に起因することを要求されます。特定疾病は下記の16種類が指定されています(介護保険法施行令第2条)。 4、認定の有効期間・更新認定 要介護認定の有効期間は、認定の効力発生日からその月の末日までとそれ以降6か月間が原則です。 有効期間満了後も要介護状態に該当すると見込まれるときは、有効期間満了日の60日前から満了日までに更新認定申請を市区町村役場に行わなければなりません。 |
|||||||||||||
| ② 保険給付 保険給付は大きく分けて3種類あります。 1、介護給付…要介護状態に関する保険給付 2、予防給付…要支援状態に関する保険給付 3、市町村特別給付…1・2の他、要介護・要支援状態の軽減又は悪化防止に資する保険給付として条例で定めるもの |
| ③ 介護給付の種類 介護給付は全部で14種類あります。 1、居宅介護サービス費(1割負担) 居宅において介護を受ける場合に、都道府県知事指定の指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき 2、特例居宅介護サービス費(1割負担) 要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けたとき等市区町村が必要があると認めるとき 3、地域密着型介護サービス費(1割負担) 市区町村長指定の指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき 4、特例地域密着型介護サービス費(1割負担) 要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護サービスを受けたとき等市区町村が必要があると認めるとき 5、居宅介護福祉用具購入費(1割負担) 居宅要介護被保険者が、入浴・排泄等の用に供する福祉用具その他福祉用具を購入したとき 6、居宅介護住宅改修費(1割負担) 居宅要介護被保険者が、手すりの取り付けその他の住宅改修を行ったとき 7、居宅介護サービス計画費(負担なし) 居宅要介護被保険者が、都道府県知事指定の指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき 8、特例居宅介護サービス費(市区町村が定めた額を負担) 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けたとき等市区町村が必要があると認めるとき 9、施設介護サービス費(1割負担) 都道府県知事指定の介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、都道府県知事指定の介護療養型医療施設の介護療養施設サービスを受けたとき 10、特例施設介護サービス費(1割負担) 要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けたとき等市区町村が必要があると認めるとき 11、特定入所者介護サービス費(食費並びに居住費の負担限度額を負担) 要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情を斟酌して厚生労働省令で定めるもの(特定入所者)が、一定の指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービスを受けたとき 12、特例特定入所者介護サービス費(食費並びに居住費の負担限度額を基準に市町村が定めた額を負担) 要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けたとき等市区町村が必要があると認めるとき 13、高額介護サービス費(同一月内に下表の金額を限度に負担) 所得区分に応じて同一月内に世帯合計で下表の金額を超える自己負担額を支払ったとき
所得区分に応じて、8月から翌7月までに支払った要介護被保険者にかかる介護費負担額及び医療費負担額が下表の金額を超えるとき
|
| ④ 予防給付の種類 予防給付は全部で12種類あります。
|
| ⑤ 市町村特別給付 市町村特別給付は、介護給付・予防給付では行き届かないところを市町村の判断で条例で定めることにより、給付を行うものです。各市町村により内容が異なりますが、愛知県知立市では下記の給付を行っています。
|