

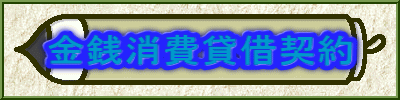
親しい間柄の者とのお金の貸し借りはついつい口約束だけで済ませがちになり、ついには貸したことをうやむやにされ
て泣き寝入りをしてしまうことが少なくありません。「親しき仲にも礼儀あり」、貸し借りはきちんと清算できるよう
契約書で証拠を残しましょう。
① 金銭授受の事実の明示
金銭消費貸借契約書を交わすに当たり、金銭授受が行われたことをまず明示しましょう。
② 弁済期間・方法
トラブル防止のため、弁済期間・方法(期日・金額・金銭授受の方法等)について明確にする必要があります。
③ 利息
利息はその元金に合わせて利息制限法第1条に定める上限利息を超えないように定めることが必要です。また、遅延損害金につ
いても、第4条で第1条の利率の1.46倍以内という制限があることに注意しなければなりません。
④ 「期限の利益の喪失」…債務者が債務の履行期限までは債務を履行しなくてもよいという「期限の利益」を失わせること
貸金を分割払いで弁済させる場合は、弁済が滞ったときに期限の利益を喪失させることができる条項を設けておきます。
⑤ 連帯保証人
貸金の回収を確実にするために、連帯保証人を付けさせるか、担保を用意させます。
⑥ 公正証書作成
債務者及び連帯保証人に対し、本契約と同一の約定による強制執行認諾約款付公正証書の作成を義務付けます。これにより、裁
判所の支払督促の手続を経ることなく債務者の財産から貸金を回収することができます(民事執行法第22条5号)。
「金銭消費貸借契約書例」では、個人間の金銭消費貸借契約の例を挙げます。