

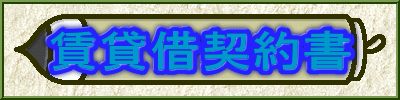
賃貸借契約といえば、住居や店舗スペースなどの不動産が主な目的物になりますが、ときには自動車や建設機材などの動産
が目的物になることもあります。ここでは建物賃貸借契約書の作成ポイントを紹介しましょう。
① 物件の表示
賃貸借の対象となる物件を具体的に表示します。所在地・建物構造・床面積は必須事項です。
② 使用目的
貸主としては使用目的を明確にして借主にそれを遵守させることを約せば、用法遵守義務違反を理由に容易に契約解除をするこ
とができるようになります。
借主としてはそれを防ぐために、できるだけ使用目的を抽象的又は概括的にしておきたいところです。
③ 賃貸借期間
賃貸借期間は契約の根幹をなしますから、明確に表示する必要があります。
1年未満の建物賃貸借契約は借地借家法第29条1項の規定により、原則として期限の定めのないものとみなされます。
それによって、貸主はいつでも解約を申し入れることができますが、そのためには貸主が使用する等の正当な事由が必要になりま
す(同法第28条)。
④ 賃料
賃料を表示しないと争いの原因になります。また、賃料前払い制の場合はその旨を特約しておく必要があります。
⑤ 修繕費用
賃貸物件の修繕費用は、故意に破損させたものを除いて貸主が負担することになっている(民法第606条1項)ので、それに違反し
ないように当事者の修繕費用の負担責任を明記しておかなければなりません。
⑥ 敷金・保証金の清算
トラブル防止のため、敷金・保証金の償却方法はできるだけ明確にし、残金の清算時期及び方法を明記します。
⑦ 原状変更の禁止・原状回復義務
貸主としては物件に手を加えられることは避けたいため原状変更禁止条項を付することがありますが、小規模な原状回復に承諾を
与えた場合等に備え、契約解除時の借主の原状回復義務(民法第545条)を明記します。
⑧ 造作買取拒否
借地借家法により、借主が貸主の許可を得て設置した造作は、契約終了の際に、借主の請求があれば貸主は時価で買い取らな
ければなりません(第33条1項)。ただし、特約を設けておけばこの規定の適用を免れることができます。
⑨ 転貸禁止
民法第612条1項に貸主の承諾を得れば転貸が可能である旨の規定がありますが、この規定の適用を排除するために、転貸禁止
の特約を設けておきます。
⑩ 契約解除事由
貸主の立場から、借主に賃貸借契約の継続が困難であると認められる事由が生じた場合は即座に契約を解除できるようにするた
め、無催告解除に関する規定を設けます。
⑪ 契約終了後の処理
トラブル防止のため、契約終了後の処理として、目的物件の明渡方法や原状回復の方法についても明確にします。
⑫ 契約終了後に残された物品の処理
退去後、目的物件内に残された物品は、所有権はまだ借主にあるため自由に処分することはできません。そこで、残された物品
については借主はその物品の所有権を放棄する旨の規定を設ける必要があります。
⑬ 原状回復費用
目的物件を通常に使用する範囲内においての劣化・汚損についての原状回復費用は貸主が負担することになっています。それ以
外の故意・過失による劣化・汚損については貸主が負担します。それぞれの費用負担の境界線を明確にしておくことが必要です。
⑭ 占有回復権
借主が長期に渡り目的物件を使用しない場合に貸主が占有回復を容易にできるように、使用休止時の貸主の占有回復権につい
て明記しておきます。
⑮ 連帯保証人
借主からの賃料回収や原状回復の不能に備えて、それ相応の連帯保証人を付けてもらうようにします。
「賃貸借契約書例」では、以上を踏まえて、個人がマンションを他人に貸す場合の賃貸借契約書を例示します。